Sweet Suite
スイート・スイート
カラリとロックアイスがグラスの中で崩れた。琥珀の液体が揺れる。ゆらゆらと波打つ水面に、ぼんやりした顔の私が映っている。空虚な顔。何かが抜け落ちてしまったような、どこかに置いてきてしまったような、誰かに奪われてしまったような、そんな顔だった。
バルコニーの縁にグラスを置いて、満天の星空を見上げる。ゆっくりと吐き出した溜息がぬるい夜風に溶けた。夜色の空は、深い藍色のビロードに宝石箱の中身をぶちまけたみたいだ。統率感なんてまるでない、そこが綺麗だと思う。
ビロードにひときわ白く輝いて見える筋がある。ミルキーウェイ、天の川。イタリア語では“Via Lattea”というらしい。遮るものなんて何もない、高層マンションの最上階だからこそ見られる景色。地上からでは街明かりに邪魔されて星なんてほとんど見えない。
日本じゃ天の川と言えば七夕、短冊にお願いだけれど、イタリアではそんなイベントはない。七月七日はただの夏の一日。六日の翌日で、八日の前日。ただそれだけ。お願いごとを思い浮かべることもなければ、織姫と彦星のために天気を心配することもない。
しかし、やはり日本で染み着いた習慣か、イタリアに来て七年が経とうとしている今も七月七日というとどうしても空を気にしてしまう。きちんと晴れただろうか、織姫と彦星は会えただろうか、なんて。淡くはじけてしまいそうな、ふわふわとした感情。子供の頃の夢を思い出すようなくすぐったさ。
子供の頃の夢なんてものは、やがては破れてしまったり色褪せてしまったりするものだが、美しい七夕の伝説もまた然り。
……二人が一緒にいられなくなったのは自業自得であると知ったのは、確か高校の頃だった。
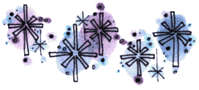
昔々、天の川のそばに天の神様が住んでいました。天の神様の一人娘、織姫は、機を織り神々の着物を作る仕事をしていました。やがて織姫が年頃になって、天の神様は織姫のためにお婿さんを探します。
そして見つけたのが、牛飼いの彦星という若者でした。
美しい織姫と立派な若者である彦星は、相手を一目見ただけで心底惚れ込み、結婚してからも楽しく幸せに暮らしました。
けれど、あまりにも互いを愛しすぎ、二人は仕事を放棄してまで遊び暮らしていたのです。その堕落ぶりに神様が怒り、二人を川の対岸に引き離してしまいました。
それからの織姫があまりに嘆き悲しむので、見かねた神様は年に一度だけ会うことを許してくれました。
それが七月七日、七夕の日です。
……というのが、伝説の全貌。
神妙な顔の友人から語られたお話は、織姫と彦星に悲劇的ロミジュリ的なラブロマンスを夢見ていた私にはちょっとした衝撃だった。しかも、高校生という年頃のせいだろうか、神様が怒るくらいの二人の堕落した生活というものを深く考えてしまったものだからいけない。
この年になれば、愛し合う男女の行き着く先に何があるかくらい知っている。二人が肉欲に溺れ仕事を放棄したのだろうかと思って、私はなんとも苦い気持ちになった。
甘い砂糖菓子のような清らかな伝説が、道ばたに捨て置かれるグラビア雑誌に転落したような感覚だった。
「遊んでばっかりなんだから、神様が怒ってもしょうがないよね」
彼女は深く頷きながらそう零す。学校からの帰り道、下校時間ぎりぎりまで残っていた私たちはチャイムに追い立てられるように校舎を出て、夕暮れの並盛をのんびりと歩いていた。
彼氏もちの友人は、独占欲の強い彼にバイクに送られて帰ることが多いのだが、週に一度だけは私と一緒に帰ってくれる。我が侭を聞き過ぎると彼に舐められて後々大変だから、というのが彼女の言い分だけど、あの唯我独尊に逆らえる時点で私はすごいと思う。高校から並盛に来た私はよく知らなかったが、彼女の彼氏は何かと有名な人だった。
「でも、それくらい好きになれる人がいるのって……少し、羨ましいかも」
周りが見えなくなるくらいに愛せる人なんて、そう出会えるものではないと思うのだ。全てを放り出して愛して、しかもそれを相手も受け入れてくれる。酷く魅惑的な世界に思える。自分と相手しかいない二人っきりの世界。綺麗でも清らかでもないけど、その匂い立つ薄暗さと痺れるような甘さは私には遠くて、だからこそ憧れるものがあった。
私が今まで思い描いていた七夕が綿飴なら、今日知った七夕の物語はチョコレートだ。
チョコレートの世界を知らない悲しきフリーの私がそう零すと、彼女はにまにま笑って私を小突いた。
「何言ってるの、ちゃんだっているじゃない」
「え? 誰のことよ」
「とぼけたって駄目だよ、私ちゃんと知ってるんだから」
悪戯っぽく目を輝かせる友人に、彼女の言わんとしていることを察して私は小さく肩を竦めた。
あれはそんなんじゃないのだ。何度も言っているのに。
「なあにそれ。知ってるって言うなら名前言ってみたら」
ここで私から名前を出したら、どうせ「私は彼のこと、なんて一言も言ってないよ? やっぱり意識してるんじゃない!」なんて喜ばせるのがオチだ。
ふん、とそっぽを向くと、彼女はもう一度私を小突く。……これが地味に痛い。
完全に一般人の私と違って、彼女のほうはちょっとばかり腕が立つらしい。というのは彼女の談であり、彼女を知る後輩くん三人組からするとちょっとどころではないらしいのだが、私は彼女が戦っている場面を見たことがないので彼女の言を信じることにしている。
「まったくもう、わかってるくせに!」
「わかんないわよ。わかりたくもないし」
「意地張るのはいいけどさ、そうしてると絶対後悔するよ?」
「しないわ」
「絶対に泣いちゃうよ?」
「誰が泣くのよ」
「だから、骸くん!」
にっこり顔の友人が挙げた名前に、私はやっぱりか、と溜息を零した。
「骸が泣くわけないじゃない。あいつは血も涙もない冷血漢よ。涙なんて、一番似合わない」
中学が一緒だったせいで目を付けられた危険極まりないあの男。あいつから逃げるため、私はわざわざ隣町の並盛高校を選んだのだ。私が逃げ出したくなるようなあの男が泣くだなんてあり得ないにも程がある。地球が逆回転を始めたってあいつはいつも通り変な髪型で得意げに高笑いし続けるだろう。
「そんなことないって、きっとちゃんに会えなくて今頃泣いてるよ」
「泣くわけないわよ。それに、クロームからもそんな話聞いたことないし」
「黒曜ランド、よく行ってるんだっけ」
「あの子、目を離したらぶっ倒れそうなのよね。あと柿本くんたちにもご飯の差し入れとか。喜んでくれるし」
「骸くんは喜んでくれないの?」
「あいつはいつも『まあ食べられますね』とか『もっと色味のあるおかずはないのですか』とかっていちいちうるさいわよ。黙って食えないのかっての」
吐き捨てるように言うと、彼女はまた楽しそうに笑った。からかうような目から逃げるように顔を背けると、吹き出すような笑い声が聞こえる。……何もおかしいことなんて言ってないのに。
「文句言いながらも食べてくれるんだね」
「そうまでして食べて欲しいとは思わないけどね」
「でも、ちゃんのご飯食べるために、わざわざクロームちゃんと入れ替わるんでしょう?」
この友人はどうにかして骸と私の間を色恋に結びつけたいらしい。
いい加減嫌になったので、多少強引とは知りつつも話をずらすことにした。うまく骸から逸れてくれればいいのだけど。
「……ちゃんとクロームって、ファミリーとかいうのなんだっけ? えーっと……カルボナーラ?」
パスタの名前みたいな集団だった気がして適当に言ってみたら、見事に外れだったらしい。彼女は小さく吹き出して首を横に振った。
「違うよ、ボンゴレ。ボンゴレファミリー。骸くんもそうなんだよ」
「……へえ」
もう骸はいいってのに。
うまく引き戻されて小さく舌打ちをすると、彼女は楽しそうに笑った。こちらの考えなんてバレバレってことか。わかってはいたけど。
「骸くんとクロームちゃんは二人で一人なんだよ。どっちも欠けちゃいけない大事な仲間なの」
「クロームがいるから骸は存在して、骸がいるからクロームも生きてる、でしょ。中学の時に骸から散々聞かされたわよ。『僕の可愛いクローム自慢』と一緒に。実際に入れ替わるとこ見なきゃ、どこの痛いカップルだって感じだけどね」
「骸くんとクロームちゃんは、お互いに必要とし合ってはいるけど、恋愛とは違うと思うな」
そう言う彼女は、今までとは少しだけ雰囲気が違うようだった。
「もちろん、私が二人に対して思ってる仲間とか、そういうのとも違うんだけどね。……あの二人の間にあるのは恋じゃないよ。愛は愛でも、友愛とか親愛とか。家族愛に近いものだと思う」
言いながら彼女は立ち止まり、吸い寄せられるように空を見上げた。薄雲が漂う空は、橙から紫、そして藍へと美しいグラデーションがかかっていた。一番星はもう澄まし顔でその身を輝かせている。黄昏時。
「でも、恋愛は違うの。もっと激しくて、もっと静かで、もっとどうしようもないの」
うっそりと空を見上げる彼女の横顔は、同性の私から見ても酷く魅力的だった。しっとりと艶めいて、ほんのりと翳りがあって、誰かに魂を明け渡してしまったように空虚で、それでいて零れ落ちそうなほどに満ち足りた感情が見える。
「私ね、織姫と彦星の気持ち、少しだけわかるんだ」
甘やかな声の向こう側に、彼女が魂を明け渡した人がいる気がした。
「好きで好きで、それ以外見えなくなっちゃうの。それはすごく怖いことだけど、すごく幸せなことよ」
「……そう」
「相手がいないと、飢えて死んじゃいそうになるの。呼吸も出来なくて、苦しいの」
「……」
「骸くんは、いつも飢え死にしそうな顔してる。多分、ちゃんが傍にいないからだよ」
違うと、口で言うのは簡単だった。けれど彼女の言葉は確かな響きを持って私の中に染み込んだのだ。
飢えと渇き、息苦しさ。それは、身に覚えがある感覚だったから。
「ちゃんも同じ。こっちに来てから、骸くんと同じ目をしてる」
「あいつと、同じ?」
「骸くんから、逃げないであげて。きっと骸くんも怖いんだと思う。……ちゃんが骸くんから逃げたくなったのと同じだよ」
「……」
黒曜からわざわざ並盛高校に通う理由を、彼女に語ったことは一度もなかった。誰に語ったこともなかった。そして指摘されたこともなかった。クロームだって、私が並盛を選んだのは偏差値だと思っている。
私は黒曜生にしては勉強が出来た。だから進学校の並盛高を選んだ。そう、思われている。
それなのに、彼女にはすっかり見抜かれていたらしい。
「骸くんは素直じゃないかもしれないけど、よく言葉を聞いたら、骸くんの気持ちがわかるはずだよ。多分、私よりもちゃんの方が、ずっと骸くんのことわかってるはず。気付かないフリしてるだけ」
「どうしてそんなこと、言えるの」
漏れた私の声は頼りなさげに掠れていた。迷い子のような声。黄昏の空気に溶けて、見えなくなる。
「女の勘、かな!」
にっこり笑って振り向いた彼女は、いつもの彼女だった。
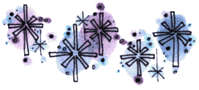
「いい年した女性が下着姿でバルコニーで一人酒とは、感心しませんね」
後ろからかかった声に、私は振り向かなかった。気配を消して入ってくるのはやめろと何度も言っている。まあ、いきなり幻術でバルコニーに降り立たれるよりは、ちゃんと玄関から入ってくる方がましだけど。
合鍵を渡すまでは、窓から不法侵入なんて日常茶飯事だったのだ。この犯罪者め。
「下着とは失礼ね。これはワンピースよ。お風呂上がりで暑いんだからいいでしょ」
「それ一枚では下着も同然じゃないですか。ほら」
言いながら、つう、と剥き出しの背中を撫でられる。またからかいに来たのだろうかこの自由人は。身を捩るだけで振り向かずにいると、こつんと肩に顎を乗せられる。絹糸みたいな藍色の髪がさらりと頬に触れた。
「お風呂出たら着込みたくないの。それに、誰にも見えないでしょ。ここ最上階よ?」
「そういう問題ではありませんよ。僕の気分がよくないんです」
「あんたの心情なんか知らない」
縁に置いていたグラスに手を伸ばすと、私よりも先に黒手袋の手がそれを奪った。肩の重みが消え、私の隣に立ったと思うと、氷に溶けて薄まったそれを思い切り煽る。
そしてしかめ面。
「何ですかこれは……麦茶?」
「酒だなんて一言も言ってないでしょ」
綺麗な顔を歪めて舌打ちをすると、やや乱暴に私の手にグラスを押しつけた。
自分で勝手に勘違いしといて何様だこの男は。
「少しくらい酔っていてくれればいいものを」
「私が素面じゃ悪いわけ?」
「素面のあなたは口が悪い」
「あんたには負けるわ」
「酒が入ったあなたは素直で御しやすいのですがね」
「クロームは素直で可愛いのにね?」
そう言えば大抵、こいつは「そんなにクロームが好きですか!」とか言って拗ねて戻るのだ。
そしてちょっとだけ後悔した私が可愛いクロームに慰められるのがオチ、なんだけど。
「……戻らないの、あんた」
今日のこいつは姿を変えなかった。霧も出てこない。隣の男を見上げると、赤と青がびっくりするくらい優しい色を滲ませて私を見つめていた。
優しくて切なくて、苦くて甘い、息が詰まるような色。
「」
体の真ん中を揺するような声だった。
ただ名前を呼ばれただけなのにどうしようもなく泣きたくなるような声だった。
「戻って、来たんです」
「え?」
「戻って来たんですよ。僕はもう、夢でも幻でもありません」
言いながら、骸はぴったりと手を覆う革の手袋を外した。
無造作にそれを落として、長い指を伸ばす。冷たい指が私の頬に触れる。私の存在を確かめるように、輪郭をなぞっていく。私ではない人間の体温が、私の頬を伝っている。
それを夢のようにぼんやりと受け入れる私に、目の前の男は少し呆れたような表情を浮かべた。
両手で頬を包み込むようにしてそっと上向かされると、色違いの目でしっかりと見つめられた。うるんだ赤と青が、瞬きのたびに熱を零している。
ゆっくりと額を近付け、こつりと合わせる。鼻先が触れ合った。
吐息が混じりあう距離で、囁くように言葉を紡いだ。
「ただいま、」
低い囁きが私の心にじわじわと沁みて行く。空っぽだった私の中身が埋まっていく。
傍にいるのに遠かったこの人が、現実味を帯び始める。
「骸」
唇が震えた。瞬きとともに涙が零れて、それを骸が低く笑う。骸の冷たい手に、湯上がりでまだあたたかな自分の手を重ねた。
「僕はここにいます」
「うん」
「僕が、僕の手があなたに触れている」
「うん」
「そしてあなたが、僕に触れているんです。本当の僕に」
「うん」
喉がつかえて言葉が出なくて、頷くことしか出来なかった。それでも骸は責めたりせず、蕩けるように甘い声で囁きを重ねた。
「やっと、会えましたね」
「骸……っ!」
「もっと呼んでください。僕の名前を、あなたの声で聞かせてください」
「骸、骸……、むく、ろっ、」
目の前の確かなリアルに、リアルの想いを乗せていく。
「……おかえり、なさい、骸」
「ええ。ただいま」
もう一度繰り返して、骸の唇が私の言葉を封じ込めた。
- Back -
