ぱちぱちと口の中を弾け喉を滑り落ちていくそれは、今まで口にしたあらゆるものの中で一番の美味だ。美味。文字通り、美しさをそのまま味わっているような感覚である。この先の一生をかけても、二度とこの味と並ぶものを口にすることは出来ないだろう。いたって平凡な私には身に余るどころか、たった一滴ですら私の価値と天秤にかけてこちらが勝るかどうか怪しい。
極上の美酒を私に振る舞う目の前の男もまた、美しさの権化だった。紅玉のような瞳を細めて優美に微笑み、グラスを傾けているだけでも絵画のようである。私が画家であれば、すぐさま筆を折りたくなるほどの美しさ。この美を一枚の額縁に収めることなんて、悪魔に魂を売っても出来はしまい。
「どうした雑種、惚けた顔をして。それほど美味かったのか?」
ギルガメッシュがシャンパングラスを軽く揺らせば、中の酒がシャンデリアから溢れる暖色の光を受けてきらきらと輝く。まるでアーチャークラスの彼が身に纏う黄金の鎧のように眩い。思わず目を細めると、ギルガメッシュは愉快そうに口を開けて笑った。
「フハハハ、そうか貴様、我の玉体に見惚れたか。良い、許す。今宵は特別にな。なんなら触れても構わんぞ?」
ギルガメッシュはグラスをテーブルに置き、ゆっくりと足を組み替えた。そして自らが座るソファの隣をぽんと叩く。
私はその全ての動作を、馬鹿みたいにじっと見つめた。細いグラスのステムを摘む指の、爪の形の美しいこと。普段よりも足元を覆う布は増えているはずなのに、細身のパンツから浮き出る太腿の筋肉質なラインが妙に艶めかしいこと。それから七分丈のシャツから伸びる腕の筋肉の隆起や、彼のためにデザインされたと思うほど肌に馴染んでいる黄金のアクセサリーの一つ一つが、彼の動きに合わせてしゃらしゃらと揺れるさまを。
息を呑む。かろうじて溶け残っていた理性のようなものが、手元のグラスに残っていたシャンパンを口に運ばせた。半分ほど残っていたそれを一気に飲み干して、再び、視線は目の前の男に吸い寄せられる。喉を滑るときは冷たく心地よかったシャンパンは、胸元まで落ちる頃にはアルコールの熱だけが残ってじりじりと内側を焦がした。
ゆっくりと、瞬きをする。意識の高揚は、ぼんやりとした心地よさは――、全て、お酒の、せい。
「此度を逃せば、おそらく次はないだろうよ。……見ているだけで良いのか?」
確かに、次など来ないだろう。南国の陽気な空気は、かのギルガメッシュすらこうも上機嫌にしてしまったのだから、全く恐ろしいばかりである。しかし、霊衣をバカンス仕様に変えても、どちらかと言えば気性が穏やか(あくまでもどちらかと言えば、である)なキャスタークラスであっても、彼はギルガメッシュ。酷薄で無情な暴君だ。なにが彼の気を損ねるか知れたものではない。触れて良いと言ったその口が、次に私の死を宣告してもなんらおかしくはないのだ。
冷静に、なるべきだ。アルコールに靄のかかった頭の奥は、静かに警鐘を鳴らしている。命が惜しければ手を伸ばしてはいけない。直接見つめることを許されているだけでも驚くべきことなのだ。その彼に、私の手で、触れるだなんて。
くつくつと喉の奥で笑い、ギルガメッシュはソファの肘掛けに腕を預け、手の甲に顎を乗せた。私がどうするのかを見て楽しんでいるのだろう。真っ赤な瞳が私の頭から爪先までを舐めるように這い、最後に私の目を見据えて止まる。酒に浮かされた私の奥底で揺らめく葛藤を、きっとあの瞳は全て見透かしている。その上で待っているのだ。誘いに乗るのか、乗らないのか。誘惑に勝つのか、負けるのか。
逃げるのか、それとも受けて立つのか。
空のグラスをテーブルに置く音が、いやに、響いた気がした。頭の奥の警鐘は一向に鳴り止まない。わかっている。
わかっていた。
短くない付き合いで、この男がいかに危険な存在であるか、私が骨身に染みて理解したのと同じように。この男もまた、私という人間の愚かしさを熟知しているのだ。
私は立ち上がり、目の前の男をじっと見つめ返す。これは賭けだ。明日まで彼の機嫌が続くか、夜を超えず彼の気が変わるか。私の命を賭けたゲームだ。
だったら勝機はある。なんせ私は数多の英霊の中からこのギルガメッシュを引き当てたのだ。私ほど運の良い人間が他にいるだろうか。世界一運が良いといっても過言でない私が、生死の二択程度、乗り越えられないわけがない。そうやって、今まで彼の提示する試練の前で、私は己を奮い立たせてきた。
「触れるって、どこまで許してくれるの?」
弱気を見せたら負けだ。たとえあの紅玉には全て見透かされているとしても、手放してはいけないものがある。晒してはいけないものがある。それは私の命綱に等しい。
「そうさな……試してみるか? 貴様にその度胸があればの話だが」
ギルガメッシュはシャツのボタンを一つ外した。しゃらりとネックレスが揺れ、引き締まった胸板が覗く。彼の全盛期に比べれば控えめだが、それでも美しさでは一点も劣る所のない彫刻のような肉体美。しかし呼吸に合わせてわずかに上下するのが、作り物でないことを知らしめている。
隣に腰を下ろし、手を伸ばす。もう、引き返せない。引き返さない。
私の冷たい手が、ギルガメッシュの頬に触れる。滑らかでしっとりと吸い付くような、それでいて張りのあるしっかりした肌が、私の手のひらを柔らかく押し返す。作り物のように美しく、あたたかい生身の肌だ。指先を滑らせて撫でるだけで、うっとりとしてしまいそうになる。
「触れるのは、手だけ?」
「試してみよと言ったであろう」
愉しげに歪められた唇に、私はもう一方の手を伸ばす。ギルガメッシュの唇が人並みに柔らかいことに、なぜかひどく驚いた。
瞳を上げれば、彼の真っ赤な双眸がこちらを見下ろしていた。その目に不快の色はない。むしろ、もっと愉しませてみろと言っている気さえした。
唇で遊ばせていた手を頬に戻し、もう一方の手もギルガメッシュの頬に添える。拳一つ分ほど空いていたスペースを詰めて、彼にぴったりと身を寄せた。えも言われぬ良い香りがふわりと漂い、かつてない距離の近さを実感してめまいがする。あのギルガメッシュに、触れている。
そして私は、触れるだけですまないことを、しようとしている。
瞼を下ろし、愉しげに光る紅を視界から遮断する。落ち着くために深く息を吸い込めば、先ほど感じた彼の香りが胸を満たした。ゆっくりと吐き出し、顔を、近付け、――
「遅い。我を待たせるな」
低く艶のある声が鼓膜を揺らし、思わず目を開けば、私の唇はギルガメッシュのそれと重なっていた。
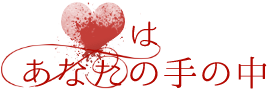
- Back -
